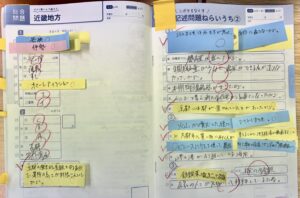皆さん、こんにちは。i-form代表の斉藤です。
先日、ある小学校の国語の授業で、『ごんぎつね』を読んだ小学生たちが
「この場面は、死んだお母さんを鍋で煮て消毒しているところだと思います」
と話していたという衝撃的な記事が、話題になっていました。
本来この場面は、葬儀の準備をしている村人たちが参列者にふるまう料理を煮ている描写。
しかし多くの子どもたちが、それを「死体を煮ている」と解釈していたのです。
もちろんこれは、ふざけて言っているのではありません。子どもたちは真剣にそう考えていたとのことです。
なぜこんな誤読が起きるのでしょうか?
このような読解ミスは、単なる国語の苦手ではなく、
語彙力・生活経験・背景知識の不足が重なって起こります。
「かまど」「よそいきの着物」「葬儀の風習」などの言葉や文化に触れたことがなければ、描写から正しくイメージすることができません。
読解力とは、文字を読む力だけではなく、言葉の背景を理解する力も含まれているのです。
<読解力を育てるために家庭でできること>
今の子どもたちは、読書量も生活体験も昔に比べて減っている傾向があります。
だからこそ、ご家庭で意識してできることがあります。
・本を読んだ後、「どんな話だった?」と会話する
・日常の中で聞きなれない言葉を説明してあげる
・ニュースや昔話などを親子で一緒に見聞きする
「読める子」は、こうした日常の積み重ねで育っていきます。
塾としても、読解力を育てる工夫をしています
i-formでは、国語の授業でも「なぜそう思ったのか?」を大切にし、背景や語彙を一緒に確認しながら読む力を育てる指導を行っています。
もし、お子さんが「なんとなく国語が苦手そう」「物語の内容がずれている」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
読む力は、すべての教科の土台です。今からでも十分、育てていくことができますよ。